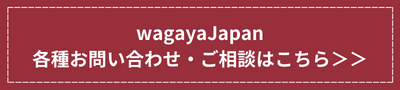地震大国日本で暮らすために知っておくべきこと!効果的な地震対策まとめ
2025-07-21
日本の文化・慣習

日本は世界有数の地震大国であり、日本列島の大半が地震リスクを抱えています。
その理由は、日本の国土が複数のプレートの境界に位置しているためです。
日本では発生タイミングの予測が難しい地震災害に向けて、さまざまな対策が用意されています。
外国にお住まいで、これから日本に暮らそうと考えている方・すでに日本に暮らしている方は、日本の地震対策や必要な備えを知っておくのがおすすめです。
今回の記事では、日本で暮らしていく上で必要な地震についての情報をまとめました。
日本における地震災害について
日本では1年にマグニチュード4.0〜4.9の地震が約1,000回、マグニチュード5以上の地震は150回程度発生しています。(2014年〜2023年の平均)
平均すると、これだけ頻繁に地震が発生している事実には留意しましょう。
※参照:気象庁「地震について」
日本で過去に起こった大震災
日本にはこれまで何回も大震災が起きています。中でも以下の3つの震災は、多くの被害者を出しました。
【関東大震災:1923年9月1日:M7.9】
死者/行方不明者約10万5,000人
関東大震災は、首都圏で発生した地震であったこと・昼食時に地震が発生したこと・関東地方全域に強い風が吹いていたことなどの要因が重なり、約21万棟以上の家屋が全焼しました。
【阪神淡路大震災:1995年1月17日:M7.3】
死者/行方不明者約6,000人(災害関連死含む)
兵庫県南部の局所的な地域で起こった直下型地震であり、東日本大震災前までは「戦後最悪の自然災害」と呼ばれていました。多くの建物が倒壊した地震です。
【東日本大震災:2011年3月11日:M9.0】
死者/行方不明者2万人以上(災害関連死含む)
東日本大震災では、岩手・宮城・福島県を想定外の巨大な津波が襲いました。その津波の高さは、宮城県女川漁港で14.8mが記録されています。
さらに、津波の影響で福島第一原発がメルトダウンし、世界中の国々の原子力発電に関する認識に大きな影響を与えました。
※参照:内閣府防災情報のページ「関東大震災100年」特設ページ
また、地震による直接的な揺れだけでなく、津波や火災などの二次災害も非常に深刻です。
例えば、津波は海底で発生した地震によって海水が押し上げられ、巨大な波となって沿岸部を襲います。東日本大震災では、この津波による被害が特に甚大で、多くの命が失われました。
さらに、火災も地震直後に多発する災害です。ガス管の破損や電気系統のショートが原因で出火し、道路が寸断された状況下では消防車の到着も遅れるため、被害が拡大しやすくなります。

日本に今後発生する可能性がある大震災
日本では地震災害による被害を最小限に抑える目的で、高精度な予測技術を活用して発生し得る大震災を予測しています。
特に首都圏も甚大な被害に遭う可能性があると懸念されている地震が、南海トラフ地震です。
南海トラフ地震はマグニチュード8〜9クラスであり、30年以内に約80%の確率で発生すると考えられています。
その被害想定区域は、沖縄・鹿児島〜神奈川・東京・千葉・茨城までの広範囲かつ、首都圏を含みます。
自治体を中心とした災害に対する取り組み
日本の各自治体では、地震発生時の被害を最小限に抑える目的で、次のような取り組みをしています。
防災訓練の実施
災害は地域の特性によって内容が変わるため、自治体ごとに個別の対応をしなければいけません。
自治体では、防災訓練・防災イベント・防災に関する相談窓口などを通して、地域住民の防災意識を高めようとしています。
現在では、自治体の防災に関する取り組みをアプリで共有するサービスや、ゲーム感覚で参加できる防災訓練など、さまざまな手段で住民が防災についての知識を得られるようになりました。
自治体で実施する防災訓練には、積極的に参加しましょう。
多言語対応の災害情報パンフレットの配布
多くの自治体では、日本語が分からない外国の方に向けて多言語対応の災害情報パンフレットを作成しています。
いざという時に日本語のみの案内で慌てないように、事前に多言語対応のパンフレットを手に入れておきましょう。
また、内閣府防災情報のページでも、「外国人のための減災のポイント」ポスターを多言語で配布しています。
各自治体の防災情報の調べ方
自分が暮らす自治体の防災訓練の情報を探すためには、以下の方法が有効です。
l 自治体の公式ホームページで防災に関する情報を確認する
l 内閣府防災情報のページで、自治体の情報を検索する
l 自治体独自の防災情報提供アプリを活用する
l 自治体や町内会が発行する広報誌を確認する
防災訓練に関する情報や多言語対応の災害情報も、上記の方法で手に入れられるでしょう。
地震に向けて個人で備えられること
地震はいつ発生するのか分かりません。そのため、普段から自信に対する備えをしておくことが大切です。
この章では、日本に暮らす方が行うべき地震に対しての備えについてまとめました。
地震に向けて備えるべき持ち出し品・備蓄品の一覧
地震に向けて備えておくべき持ち出し品と備蓄品の一覧を紹介します。
家族の人数・性別・年齢・宗教などに合わせて、必要なものを追加してください。
【持ち出し品】
l 飲料水
l 非常食
l 携帯電話の充電池
l 懐中電灯
l 携帯ラジオ
l 予備の電池
l ヘルメットや防災ずきん
l 貴重品
l 現金
l タオル
l マスク
l 着替え
l 雨具
l ティッシュペーパー・ウェットティッシュ
l 軍手
l ナイフ・缶切り・栓抜き
l ライター・マッチ・ロウソク
l ポリ袋
l 健康保険証やパスポートなどのコピー
l 救急医薬品
【備蓄品】
l 飲料水(1人1日3リットルが目安)
l 食糧
l 毛布・寝袋
l 洗面用具
l 鍋・やかん
l 簡易トイレ
l ブルーシート
l トイレットペーパー・ティッシュペーパー・ウェットティッシュ
l 新聞紙
l ブルーシート
l 工具類
l 割り箸や紙コップ・紙皿
l ラップ・アルミホイル
防災グッズについて、より詳しい情報はこちらのページも参考にしてください。
減災のために自宅でできること
減災とは、災害発生時の被害を最小限に抑える対策のことを指します。
地震の発生はコントロール不可能なものであるため、減災により自分と家族を守ることが大切です。
以下を参考に、自宅で減災対策をしてみてください。
【家具を固定する】
持ち家の場合は釘などを使用して家具をしっかり壁に固定し、地震により家具が倒れることを防ぎます。
日本では家具を固定できる突っ張り棒などが販売されているため、賃貸住宅の方は壁を傷つけずに家具を固定する方法を考えると良いでしょう。
【高い場所に重いもの・割れるものを置かない】
地震発生時には、棚に置いてあった家具が揺れのせいで飛び出し、住民に怪我をさせてしまう可能性があります。
このような被害を防ぐためには、普段から高い場所に重いものや割れものを置かないようにする癖をつけてください。
また、火災対策としては感震ブレーカー(地震を感知して自動的に電気を遮断する装置)を設置することも効果的です。地震後の通電によって火災が起こる「通電火災」を防ぐためにも、特に住宅密集地に住む場合は導入を検討しましょう。
避難所を確認しておく
避難所は何らかの災害により自宅での生活が難しくなった人々が、一時的に生活する施設であり、被災者の安全を確保する役割を持ちます。
具体的には、学校の体育館や公民館などが指定されることが多く、日本全国に8万箇所以上の避難所が用意されています。
また、避難所とは別の意味を持つ言葉が「避難場所」です。避難場所は災害から命を守るために緊急で避難する場所を指し、災害対策基本法に基づいて災害種別ごとに指定されています。
自治体の公式サイトなどを確認し、最寄りの避難場所・避難所を把握しておきましょう。
避難場所や避難所は、災害発生後に家族と待ち合わせる場所としても使いやすいです。
津波が想定される地域では、避難所とは別に「津波避難ビル」や「高台への避難経路」も指定されている場合があります。海沿いに住む場合は、津波避難場所までの時間やルートも必ず確認しておきましょう。

災害時に使えるアプリやサイトの情報
最後に、災害時に使えるアプリやサイトを紹介します。
アプリやサイトを普段から防災のための情報収集に活用していれば、いざという時に使いこなせるでしょう。
【NHK WORLD – JAPAN「Disaster & Emergency」】
地震や津波、台風などの災害情報を英語を中心に多言語で提供する、NHKの公式サイトです。日本国内で災害が発生した際に、最新の速報や避難情報、被害状況などを信頼性の高い情報源としてリアルタイムで確認できます。動画ニュースや地図付きの速報、過去の災害に関する解説なども充実しており、日本に住む外国人や旅行者にとって心強い防災ツールです。
【多言語防災情報「Safety tips」アプリ】
地震・津波・台風などの災害情報を13言語に対応して通知してくれる無料アプリで、訪日外国人や在日外国人向けに観光庁が監修しています。地震の発生や特別警報の発令、避難勧告などをプッシュ通知で即時に知らせてくれるため、災害時にも安心して行動できます。気象情報だけでなく、避難場所の検索や医療機関の案内、交通情報へのリンクなど、災害時に役立つ多機能が備わっています。
【Japan Safe Travel(JST / 日本政府観光局)】
日本政府観光局(JNTO)が提供する訪日外国人向けの災害・安全情報サイトです。地震や台風などの自然災害、公共交通機関の運行状況、空港や観光施設の最新情報を英語でわかりやすく提供しています。また、LINEと連携して災害警報を受け取れる機能もあり、短期滞在の旅行者でも簡単に利用できます。
【Yahoo!防災速報】
Yahoo!防災情報は、地震速報のみでなくJアラートや火山情報などさまざまな情報を通知するアプリです。
ライフラインの共有情報も確認できるため、避難中にもアプリが役立つでしょう。
また、アプリのインターフェースや安否確認メールなどの一部は英語対応可能です。
【国土交通省 防災ポータル】
国土交通省が提供している防災ポータルは、災害前の防災・災害後に必要な情報を集約したサイトです。
サイト全体を日本語のみでなく、英語・中国語・韓国語を含む複数の言語に変更できます。
まとめ
地震大国である日本で暮らすためには、事前に地震についての知識を身につけ備えをすることが大切です。
この記事を参考に、今からできる防災・減災に取り組みましょう。日頃からの対策が、いざという時に家族や自分の命運を分ける可能性があると考えてください。
そして、地震そのものだけでなく、津波や火災といった二次災害に対する意識も非常に重要です。これらの災害は発生から数分〜数十分という短時間で人々の命を脅かします。命を守るためには、日常の中で「何を持ち出すか」「どこに避難するか」を明確にし、定期的に確認・更新しておくことが求められます。